抽象化と具体化は、圧縮と解凍
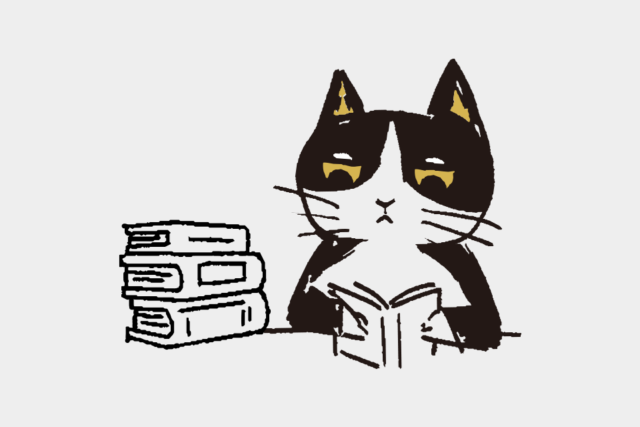
記憶容量の限界
「具体と抽象」については、このブログの中でも度々取り上げてきました。「抽象化」の目的や、それができることによる利点は多岐にわたります。その中で「情報を効率よく記憶できる」というメリットについて紹介しようと思います。大人でも子どもでも、「記憶容量の限界」を感じたことがある人は多いのではないでしょうか。一方で、どれほど記憶力のいい人がいたとしても、コンピュータの記憶容量を超えられる人間はいません。さらに言えば、コンピュータの記憶容量にも限界はあります。人でもコンピューターでも、無限に覚えることはできないのです。
圧縮や削除
コンピュータに馴染みがないのであれば、スマホでも構いません。データ容量がいっぱいになってしまい、空き容量を確保するために、データを圧縮したり、不要なデータを削除したりしたことはありませんか。情報を圧縮したり、重要度の低いものを捨てたりする作業は、私たちが「抽象化」する過程とよく似ているのです。
容量の限界を超える
ところで、学生時代に記憶力を活かして成績が良かった、という人は多いのではないでしょうか。学習段階(子ども〜学生時代)なら、勤勉さによる丸覚えで、良い結果を得られることが多かったかも知れません。ところが大人になると、自身の記憶容量はこれまでの蓄積でそれなりに埋まってきているし、学生の頃のように暗記とまで言わなくても「覚える」ことに、時間を費やせなくなってきます。では、どのように対処すれば良いのでしょうか?そこで「抽象化」の出番です。実は、記憶の際の抽象化は、無意識にできている人の方が多いように思います。
抽象化できると強い
子どもや学生を見ていると、はた目には「記憶力がよく、勉強ができる」タイプの実態として、そもそも抽象化することが得意なケースをよく目にします。そういう子は、インプット段階で自然と抽象化をしているのが分かります。「丸覚え」するのではなく、ものごとの「構造」や、ある情報のグループに見られる「一貫性や共通性」、「要するに」や「つまり」と、いったん突き詰めて抽象化したものを記憶しているのです。
センスがすべてではない
大人でも子どもでも、先天的に「抽象化」が得意な人もいます。これは「勤勉さ(真面目にコツコツできること)」と同様に、1つの性質、資質と言えるのかも知れません。しかし、勤勉さにしても抽象化の能力にしても、後天的にでも手に入れることができるものだと考えています。その資質や性質が顕著でなくても、認識して意識を向けて実践していくことで身につけられるし、すでに身についている人も、その精度を上げていけるはずです。
手ではなく、力の抜きどころ
ここで終わると「努力しようぜ!」みたいな暑苦しいメッセージに見えてしまいますが、決してそうではありません。情報をインプットすること、記憶することがゴールではないので、「力の入れどころと抜きどころ」を見極めましょう、というお話なのです。そして、そのときに「抽象化」が活躍するのだ、というご紹介でした。
| 記事タイトル | 抽象化と具体化は、圧縮と解凍 |
|---|---|
| 掲載日 | 2025年4月19日 |
| カテゴリー | ブログ |
| 表示数 | 405views |
