遊べば、学べる
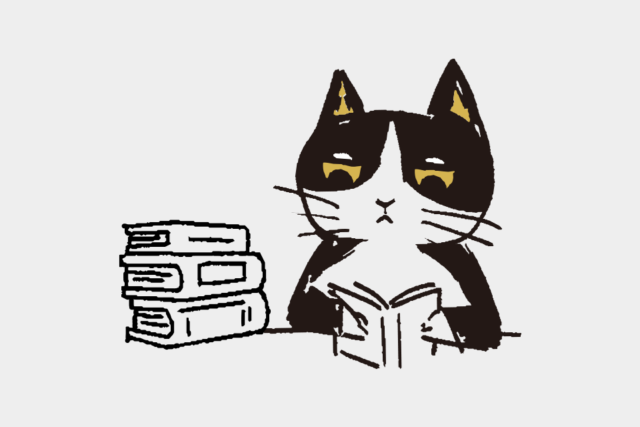
バドミントン日和
先日、近所で「バドミントンみたいな遊び」をする小学生の女の子を見かけました。正式なバドミントンのラケットとシャトル(羽)ではなく、スポンジ製あるいは同じくらい軽いプラスティックのボールを、これまたオモチャみたいなラケットで打ち合う、行楽シーズンのレジャーシーンでよく見かけるアレです。その子たちがよく一緒に遊んでいるのを目にするので、きっと仲良しなのでしょう。その日も2人は笑い転げながら、バドミントン的な遊びを大いに楽しんでいました。
競技なら屋内で
バドミントンも含めて、屋外でそれっぽい遊びをやったことのある人なら、よくご存知のことと思います。屋外だと(当たっても痛くない)軽いボールも、バドミントンのシャトル(羽)も、とにかく風に流されてしまうし、コートや互いの陣地なども不明瞭なので、競技スポーツのバドミントンとはまったくの別ものになります。そもそも「バドミントンみたいな遊び」は勝ち負けに興じるのではなく、ラリーを続けることを目指して、打ち損じたときの失敗や、しゃかりきに奮闘した姿を笑い合って楽しむものなのかも知れません。
どっちがいい?
例にもれず、近所の女の子たちの軽いボールも風に流されやすく、2人のラリーはなかなか続きません。また、2人の技量に差があるのか「ボールを拾いに行く」回数に偏りが出てきて、何となく「アンフェア」なムードが漂い始めました。すると、片方の子が口火を切り「ローカルルール」を提案しました。その際に「打つのに失敗した人がボールを取りに行くのと、ボールに近い人が取りに行くのとどっちかいい?」と、選択肢を示して、しかも相手に決定を委ねる形にしていた点に、私はすこぶる感心しました。
漂うリーダーの資質
もちろん、一部始終をつぶさに観察していた訳ではないので、実際には、提示された2択はそれほど「フェア」な条件ではなかったかも知れません。言い出しっぺの子にとっては、どちらに転んでも自分に優位になるような「ローカルルール」だった可能性もあります。ただ注目すべきは、言い出しっぺの子は「こうしよう!」と決定事項にはせず、自分のアイデアを伝えて「どうする?」と打診したところが、めっちゃ偉いなと思いました。発言力のある子の中には、「ドラえもん」に出てくるガキ大将のジャイアンみたいに、全部自分が決めてしまう子も少なくないからです。(それでも、ルールを提案できる時点で十分に立派ですが)。
ルールは改善できる
「どっちがいい?」と聞かれた子も、少し考えてから答えを出していました。その先は見届けていないのですが、もし2人がいったん決めたルールでも、やってみて不具合があったり、「アンフェア」感が解消されなかったりしたなら、再度ルールを検討すれば良い訳です。どちらの子でも構わないので「ごめん、さっきは△△って言いたけど」ときちんと言い出せて、2人で、2人が楽しくなるように考え直せたら最高だな、とその場を離れたあと思いを馳せました。
門前の小僧、習わぬPDCA
私自身の子ども時代を振り返ってみても、遊びの中で「ローカルルール」を決める機会は何度もありました。その際、教えられていなくても案外「PDCA サイクル(計画→実行→確認→改善)」あるいは「OODA ループ(観察→状況判断→意思決定→行動)」を自然と行なえていたケースもあった気がします。現在、学校教育で(おもに大人が)てんてこまいしている「探求」の授業のヒントって、こういうところにあるんじゃないかなと感じました。
| 記事タイトル | 遊べば、学べる |
|---|---|
| 掲載日 | 2025年5月3日 |
| カテゴリー | ブログ |
| 表示数 | 406views |
