ややこしい日本の漢字
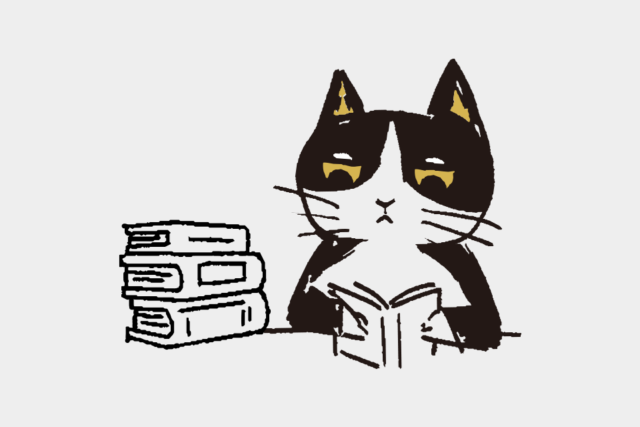
右脳とか左脳とか
日本語特有の「漢字まじり」の表記を理解することは、脳科学的な視点でも、複雑で難易度が高いようです。だからと言って日本人が他の言語圏の人より「賢い」という話がしたいわけでも、また、もっと他の言語のようにシンプルに、漢字をなくして「全部ひらがなで表記しよう」という提案をしたい訳でもありません。漢字については、その複雑さに見合うだけの効率の良さ(視覚で得られる情報量の豊かさ)があるので、100%なくしてしまうことは避けたいです。
チャイニーズ・キャラクターとの違い
一文字の表記で読み方が複数(音読みと訓読みが)あるというのが、日本語の漢字の難しさの要因です。漢字表記が中心の中国には、訓読みは存在しないと気づいたとき目から鱗が落ちました。たしかに不便さの際立つ日本の漢字ですが、一文字である程度の意味を伝えられる点は秀逸です。また漢字まじりの方が、ひらがなやカタカナのみで表記するよりもスペースを少なくできますし、見た目にメリハリがつくので(読点のような役割も果たし)読みやすさも向上します。
日本らしい独自進化
日本語の表記は、輸入してきた漢字をベースにアレンジされて「かな」という独自の表記が成り立ちました。輸入してきた漢字に加え、ひらがなもカタカナも併記されている点は、アルファベットのみで表せる言語と比べると複雑過ぎるかも知れません。けれども、その個性は文化として大切にしていきたいと思うのです。と同時に、他の言語圏の人がせっかく日本語を学ぼうとした場合に生じる「不便」にも配慮できればと感じています。そのため「やさしい日本語」は強く推奨していきたいです。
やさしい日本語
外国人に向けた日本語教育の現場にいる方からお話を聞くと、日本語学習者にとって「漢字」は大きな壁となっているようです。また、副詞(連用修飾語)例えば「ゆっくり」や「とても」、「きっと/おそらく」などの表現もネックだそうです。そのようなことをふまえて「やさしい日本語」とは、漢字にルビ(よみがな)を振ったり、できるだけシンプルな構造の文章表現を指しています。現在では、公的な施設(役所など)での案内や表記に採用されていることが多いです。もちろん「やさしい日本語」は外国からの移住者を対象にしたものですが、日本人の子どもや高齢者などにとっても「やさしい」ので、もっと日常的に活用されれば良いと思っています。
構造に注目しよう
日本人でも、漢字を処理することに苦戦している人は少なくありません。国語の個別指導をしてきたなかで、記憶力や理解力は申し分なく、むしろ優秀と呼べるレベルなのに「漢字が極端に苦手」な生徒を何人も見てきました。持って生まれた性質などもあるので、原因を一つに絞ることはできませんが、他の暗記科目のように丸覚えで対処しようとすると苦戦するのが「漢字」です。漢字の構造や成り立ちを理解すれば、同じ「覚える」作業でも、もっと効率良く定着させられますし、その上で漢字の便利さにも気づけるはずです。
ゼロか百かではなく
漢字は難しいですが、文化や歴史でもあるので全否定したくありません。でも、時代の流れと共に柔軟な対応もしていきたいです。柔軟な対応=いい塩梅でアレンジを加えていくことは、日本人の得意とするところなので、きっと良い形になっていくと信じています。世の中には、もっと深刻な無理難題が山積していますが、「森とタタラ場、双方生きる道はないのか?!」と叫ぶ「もののけ姫」のアシタカみたいに、簡単にどちらかを切り捨てない、諦めない精神を持っていたいです。
| 記事タイトル | ややこしい日本の漢字 |
|---|---|
| 掲載日 | 2025年6月28日 |
| カテゴリー | ブログ |
| 表示数 | 399views |
