単一原因の誤謬
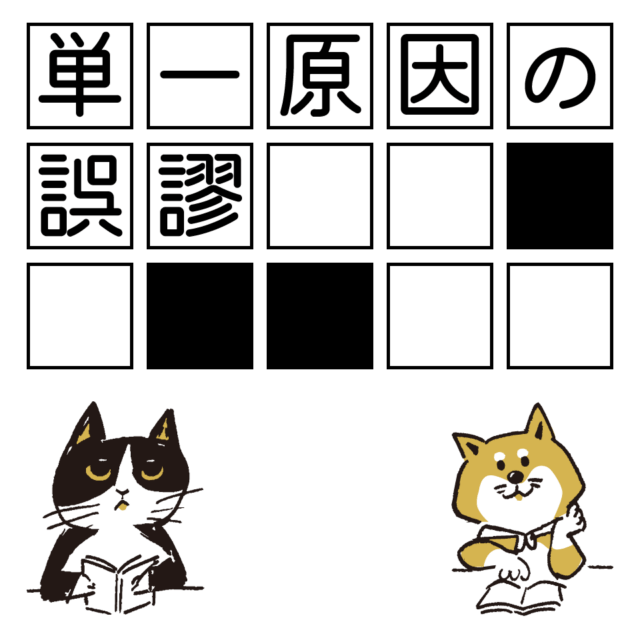
単一原因の誤謬
「単一原因の誤謬(ごびゅう)」とは、実際には複数の原因があるにもかかわらず、その原因を一つに絞り込んでしまい、結果として誤った結論にたどり着いてしまうことを指します。「因果の過剰な単純化」とも同義です。
具体的な例
例えば、「今日未明、80歳の男性が運転する車が自転車に乗った大学生にぶつかる交通事故がありました」というニュースを聞いたときに、多くの方は「高齢者ドライバーの認知能力に問題があるのでは」という原因を想像するでしょう。しかし、実は大学生が無灯火であったこと、大学生がイヤホンを耳につけたまま自転車に乗り、スマホを見ていたこと、見通しの悪い道路であったこと、男性が妻の介護で疲れていたことなど、複数の要因が重なって起こった結果かもしれないのです。
単一原因の誤謬の何が問題なのか
単一原因の誤謬の最も大きな問題は、特定した「原因」を取り除いたとしても、根本的な問題解決には至らない点です。また、その責任を一方的に負わされた個人や団体が不利益を被る可能性もあります。特定された「原因」を取り除いた側は、対策を講じた気になってしまいがちですが、結果として本質的な問題解決が遅れたり、再発防止への取り組みが疎かになったりする恐れがあるのです。
単一原因の誤謬が起こるのはなぜか
それでは、なぜ単一原因の誤謬は起こってしまうのでしょうか。一番の理由は、やはり「人間だから」という点に集約されるでしょう。人間は脳の構造上、複雑に絡み合った原因よりも、単純で理解しやすい原因のほうを自然と求めてしまう傾向があるそうです。
また、学生時代の教育の影響も指摘されています。学生時代、正解か不正解かが明確な問題ばかりを繰り返し解く練習をすることで、「すべての問題には唯一の正解がある」という考え方が刷り込まれている可能性があります。
単一原因の誤謬を避けるには
複雑な問題に直面した際は、その因果関係を徹底的に深く考える必要があります。すぐに見つかる、あるいは安易に思いつく原因に飛びつくのは避けるべきです。また、十分に考え抜いた上で原因が複数あると判断した場合は、それぞれの原因の問題に対する影響度合いを評価し、取り組むべき順序を決めていくのも効果的でしょう。
最も大切なのは、対策を講じても変化が見られない場合に、他の原因が存在することを受け入れたり、想定した因果関係が間違っている可能性を受け入れたりするなど、常に情報を更新できる柔軟な姿勢を持つことです。
