「舟を編む」
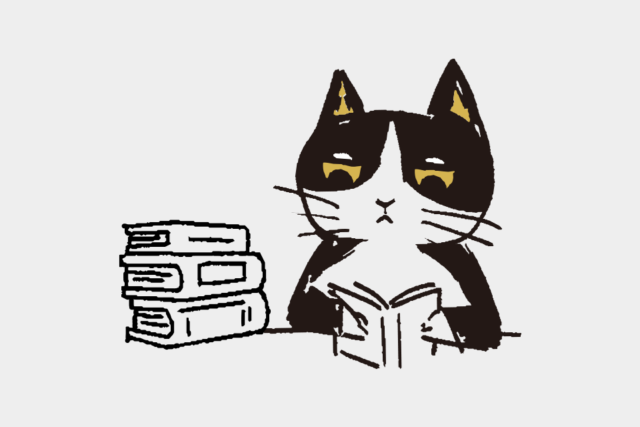
生成AI ありがとう
とうとう生成AIに人生相談までするようになった私ですが、「言語化する/言語化できる」ことの重要性を疑うことは、未だありません。なんでだろうと考えてみると、言語化する際に生成AIに期待することは、やはり体裁を整える領域から大きく外れないからだと感じています。
言語化は必要か
とは言え、「なぜ言語化が重要なのか」を上手く説明できない(言語化できていない)自身へのモヤモヤも持ち合わせていたところに、「そうだった!」と思い起こさせてくれた機会がありました。非常にベタで恥ずかしいのですが、その契機はNHKドラマの「舟を編む」でした。原作も、松田龍平さんと宮崎あおいさん主演による映画も、よく知られている作品ですが、映画では駆け足になっていた、物語の後半部分から特に丁寧に描かれているのがドラマ版です。
「舟を編む」にありがとう
「舟を編む」は辞書を作る人たちの物語です。そのため私たちの日常から考えると、あり得ないほど深く深く「言葉」について掘り下げていく登場人物たちの様子は、もはや変態の領域であり、しかしながら、その真摯さに胸を打たれることも少なくありません。
言葉の使い道
NHKのドラマ版では、もともと本の虫で言葉オタクの素養十分だった馬締(まじめ)という男性ではなく、出版社のファッション誌部門から異動させられてきた若い女性、岸辺みどりを中心に取り上げています。映画版とドラマ版の設定もろもろの違いはさておき、辞書作りの監修を務める国語学者の松本が、癌を患いながら書いた手紙の内容に感銘を受けました。
助けてくれるもの
患者が主訴だけでなく、痛みや辛さ違和感など自分にしか分からないニュアンスを言葉にできれば、患者にも治療する側にとっても大きな助けとなります。例えば意見だとか、そんな大それたことを言語化することが重要ではないと考える人も多いでしょう。でも「私はそんなことしたいと思わないし、する必要もない」という人にとっても、言葉にできることで、その人自身を助けてくれる場面が人生には必ずあります。
代替可能か不可能か
生成AIは、言語化を本当に助けてくれます。ただ、表現や思考のくせ(傾向)としての、その人「っぽさ」と、その人「自身」とは等価ではないはずです。これから価値があるのは、いびつでも下手くそでも構わないので、その人「そのもの」ではないだろうか、と真剣に感じ始めています。
| 記事タイトル | 「舟を編む」 |
|---|---|
| 掲載日 | 2025年8月23日 |
| カテゴリー | ブログ |
| 表示数 | 336views |
