先にする?後からする?
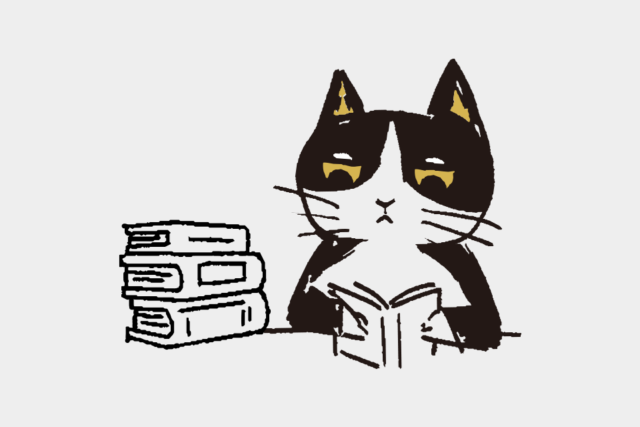
「一方的」は結構きつい
教育現場では、一方的に知識を提供する形が見直されつつあり、双方向の学びの場を実現しようとする動きがあります。たとえ現状が、インタラクティブからかけ離れていても、理想としては「双方向の学び」を掲げるようになっています。学生時代を思い起こすと「何が問題視されているのか」イメージが湧きやすいのではないでしょうか。先生が 1人で喋り続けている授業は、よほど話術が卓越したケースでない限り、眠かったり退屈に感じたりしたものです。
インプットは必要
「学び」とは、知識のインプットのみを指していません。「問いを持ち、探究する中で、新しい発見や創造をすることが本質」と、AIもまとめています(辞書より良いこと言ってますね)。とは言え「問いを立てる」のも「探求する」のも、知識を持たずして成し得ないのも事実です。どこかのタイミングで知識のインプットは欠かせません。
反転学習
「反転学習」とは、予習してから授業に臨むことなのですが、通常の「予習」との違いは、学習者による予習の質にムラが出にくいようになっている点です。たとえば、動画などで知識(従来の授業内容)がまとめられたものが学習者に提供されるので、予習の仕方が分からなかった学習者でも比較的適切に取り組むことができます。
アウトプットを実現させる
「反転学習」のメリットは決して、見やすくまとまった動画で知識をインプットできる点ではありません。対面での授業にしろ、動画にしろ、受動的なインプットには限界があります。どのような知識も、聞くだけ、見る(読む)だけでは「分かったつもり」の領域に留まりやすいです。そこで、「反転学習」の授業では「分かったつもり」を「分かった」に近づけるために、学習者同士や教師も交えたやり取りを行います。このインプットをふまえた上でアウトプットの機会が設計されている点が「反転学習」のメリットと言えます。
後回しにするとき
もちろん「反転学習」は、初等教育の段階には不向きですが、ある程度の年齢や水準をクリアした学習者を対象とした場合、具体的には高校生以上なら、本来の「学び」を実現させるために有効な形と言えます。一方で、「学び」という場面ではなく、単純に自身の感覚を研ぎ澄ませたい、あるいは感性と向き合いたいようなときには、知識のインプットは後回しにした方が良いかも知れません。
「鑑賞」のスゝメ
先日、現代アートにまつわる講座を拝聴する機会がありました。現代アート鑑賞のセオリーとしては「ただ感じろ」らしいのですが、やはり古典的なアートと同様に記号的なものや背景知識を持っている方が楽しめるのも事実のようで。個人的に、その講座で最も共感した部分は「予備知識なしに、まず感じて自分で考える。その後で知識にアプローチしていく」という流れを薦められていたことでした。
いつするの?!
私は映画鑑賞の際には、情報(知識)は「後入れ」に徹底的にこだわっています。先に情報を入れてしまうと、作品(映画)自体を自分がどんな風に受け止めたのか、分からなくなってしまうからです。「鑑賞」という分野に限らず、たとえば旅行先の情報を先取りし過ぎて、旅行そのものが確認作業みたいになってしまう味気なさが少なからずあると思います。「インプットをどのタイミングでするのか」も、なかなか重要だと感じます。
| 記事タイトル | 先にする?後からする? |
|---|---|
| 掲載日 | 2025年10月4日 |
| カテゴリー | ブログ |
| 表示数 | 249views |
