敷衍を敷衍する
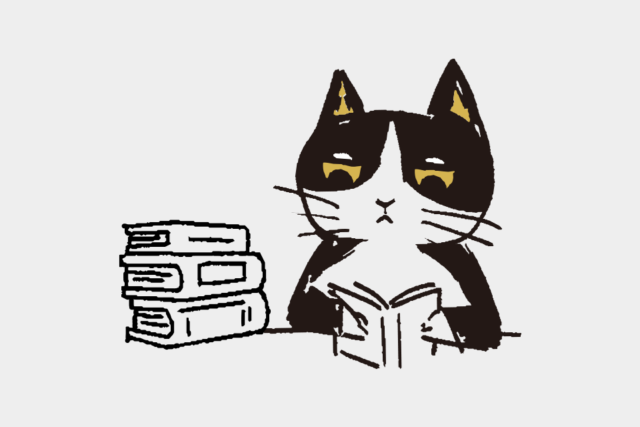
敷衍とは
「敷衍」は「ふえん」と読み、辞書では「意味や趣旨のわかりにくい所を、やさしく言い替えたり詳しく述べたりして説明すること」とされています。「敷」は漢検でいうと3級相当、一方「衍」は1級相当の難しい漢字なので、漢検1級の合格率(10%程度)から推測すると日本人でも1割未満の人しか読んだり理解したりできない難しい漢字だと考えられます。また、主に論文や公的な文書で登場する言葉なので、知らなかったことを恥ずかしがるものではないようです。
日本人の識字率
ところで、「敷衍」のように、多くの方が読めない、あるいは意味がわからない漢字があるにもかかわらず、日本人の「識字率」がほぼ100%であるとされているのはなぜなのでしょうか。少し調べてみると、そもそも識字率の定義は「日常生活で用いられる簡単で短い文章を理解して読み書きできること」であることや、常用漢字(2,136字)であれば義務教育課程で学習していることから、高度な語彙力に分類される「敷衍」を知っているかどうかは識字率とは関係がないとされていることが理由のようです。
敷衍が敷衍できていない
面白いなと思ったのは「敷衍」の意味や読みが、世の中に敷衍できていないことです。言葉の持つ意味自体は非常に素晴らしいもので、教育はもちろんのこと、広告や広報、接客など、現代のサービス業と呼ばれるあらゆる仕事の根本を指し示しています。であるにも関わらず、この言葉が敷衍できていないのはもったいないように思いました。
敷衍を敷衍する
大人になればなるほど、新しいものに触れて驚いたり、感性が刺激されることが少なくなります。特に、心地よく楽しめるようにチューニングされたエンタメコンテンツを受動的に楽しんでいるだけでは、その機会も減る一方でしょう。今後、価値観の多様化や外国人人材の増加が予想される社会において、「敷衍」の考え方は大切なツールになりそうです。新しく学んだ言葉やその意味を、思考や行動に反映できる「成長する大人」であり続けたいと思います。
| 記事タイトル | 敷衍を敷衍する |
|---|---|
| 掲載日 | 2025年10月11日 |
| カテゴリー | ブログ |
| 表示数 | 400views |
