「やればできる」の裏表
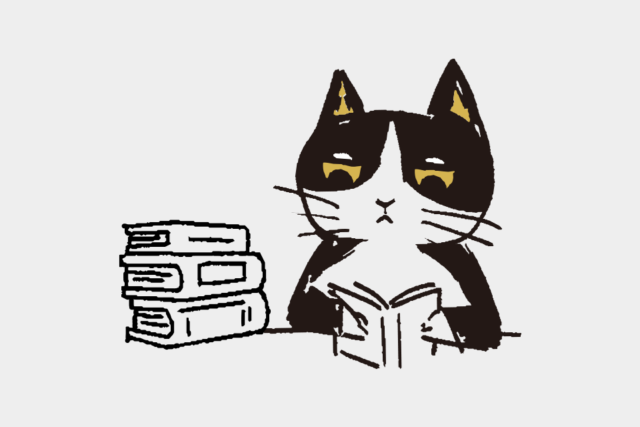
サクラサク
私が国語の個別指導を担当していた中学受験生の親御様から、「無事に志望校に合格できました」という報告をいただき、今週はとても満たされた気持ちで過ごせました。特に5年生の最後から指導を始めた女の子からは、受験前の最後の授業を終えた際に「(これまでやってきて)国語のレベルが、ひとつ上がった気がします」という言葉を聞けて、私としては「感無量」以外の何ものでもありませんでした。
涙がちょちょぎれました
受験の結果が大事なのはもちろんですが、私が個別指導を行なっている目的は「本質的な思考力を鍛えるための、国語力を育むこと」なので、受験前の生徒さんのその言葉は、合格の報告に匹敵する、あるいはそれ以上の喜びをもたらしてくれました。誤解を招かないように補足すると、私は「レベルが上がった」ことを最重要と捉えているのではなく、頑張ってきた本人が「自信を持てるようになったこと」、そして自分のやってきたことが無駄ではなかった「成果があった」と感じられたことが、学習をサポートする立場として、何より意義深いと考えています。
うざくてあたり前田のクラッカー
一方で、同じ中学受験生でも、入試の迫る状況においてさえ、授業らしい授業が成り立たないケースもありました。とにかく国語が苦手で嫌いで、指導にあたる私のことも気に入らないので「うざい」と繰り返していました。そのような子でも時折、反抗し続けるのに疲れたり飽きたりして、ふと問題に向き合うことがありました。終わらせたいがために雑な形で解答すると、案の定間違えるのですが、うざがられながらも私がしつこく考え直しを求めると、つまり本人が真剣に取り組むと、正解できるところも出てくるのです。
YDK
よく「やればできる子」という表現を教育現場で耳にします。どの立場から発するかによっても聞こえ方は変わりますが、先生(指導にあたる立場)が口にする場合には、とても注意が必要な言葉だと感じています。先生の真意を好意的に受け取ると、子どもの可能性や伸びしろのようなものを全面的に肯定して「あきらめないで」と伝えることが目的だと考えられます。けれども、受け取り方を変えると少々無責任にも聞こえてきます。実際に指導経験のある者からすると「やればできる」なんて当たり前だからです。裏を返せば「やらないからできない」のであって、それを「やるようにする」ことが巨大な関門なのです。
不撓不屈の精神で
そんなこんなで、どこかで聞いた「やる気スイッチ」というフレーズには、ある程度の納得感があります。ビジネスパーソン向けにさえ、それに近い記事もちらほら見かけます。しかし「スイッチ」と言っても、ポチッとボタンを押せば済むような単純なカラクリはなく、機能させるためには複合的だったり循環的だったりと複雑なアプローチがあるようです。とにかく指導する者として、多くの壁にぶち当たりながら痛感しているのは、こちらが「あきらめない」ことに尽きます。今後も「『やればできる子』なんですけどね〜」という逃げ口上に走らずに、七転び八起きしながら成長を促していく、そういう者に私はなりたいと誓った「サクラサク」week でした。
| 記事タイトル | 「やればできる」の裏表 |
|---|---|
| 掲載日 | 2025年1月25日 |
| カテゴリー | ブログ |
| 表示数 | 374views |
