「能やな」「能なん?」「能やん!」
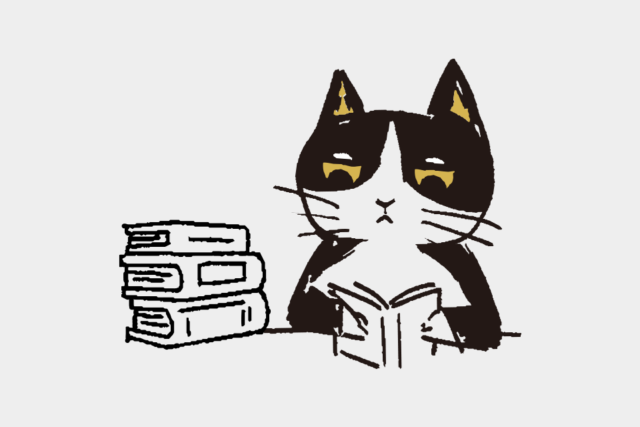
あたためていたら腐るかも知れない
先日、たまたま2日連続で「能」のビギナー講座と呼べそうなイベントに足を運んできました。何となく興味はあっても、実際にはなかなか手をつけられないことが少なからずあり、そのひとつが「能」でした。よく「リタイアして時間ができたら、たくさん旅行したい」というのを耳にします。しかし同時に「リタイア後は今より体力が落ちているのだから、先送りせず元気な今のうちに旅行した方がいい」とも聞きます。そんなこんなで、昨今は実現可能であれば「やってしまおう!」と思うようになり、今回は「能」に片足(の指の先っちょ)をつっこんでみました。
「幽玄」とか「越境」とか
そもそもは神鉄(神戸電鉄)ユーザーだった頃に、車内か駅のポスターで、神戸市北区にあるお寺で「薪能(たきぎのう)」の催しがあることを知り、「行ってみたーい」と思ったことが始まりでした。暗闇のなか篝火(かがりび)が灯された空間に、能面と装束を身につけた人が登場してくるなんて、絶対に「異世界」を感じられるんだろうなと、それは魅力的な体験に違いないと想像した訳です。先日のビギナー講座で分かったことですが、能楽(能と狂言)では「未来、現在、過去」と「現世(げんせ)/幽世(かくりよ)」という異なる次元を行き来する物語が演じられているらしいので、「異世界」を想起するのは間違いではなさそうです。
それは狂言やな
もうひとつ、ずっと気になっていた理由として、お笑いコンビ「さらば青春の光」のネタが挙げられます。コントのイメージの強い「さらば青春の光」ですが、漫才の賞レース「M-1グランプリ」の決勝に進出した際に「能」というフレーズを多用するネタをしていて、そこをきっかけに「能楽」を、もっとカジュアルに楽しんでもいいのかもと感じていました。古めかしくて何を言っているのか分からないし、格式高くて自分の身の丈に合わない感覚を抱きがちですが、お話の内容は案外と面白いものが多いと聞きます。実際に、「能楽」の中でも特に「狂言」は、漫才のルーツとされているとか、いないとか。
能ちゃうやん
2日連続の「能」のビギナー講座は、それぞれ別の企画でした。ひとつは湊川神社の神能殿で催された「桃の節句と五人囃子」というイベントで、小鼓方の人間国宝、大倉源次郎さんによる「五人囃子」の紹介や実演と、落合陽一さんを交えて行われたトークセッションでした。ふたつめは、藤田美術館で開催された「教えて能楽師!2025 初番目〜難波」で、藤田美術館の学芸員さんと能楽師のシテ方(能面を着けて謡って舞う物語の主役)、上田宜照さんによる「難波」という演目の解説でした。要するに、結局まだ「能楽」を鑑賞できていないのですが、そこはかとなく感じていた「ハードルの高さ」はかなり解消できたので、今年中に何か観に行こうと決めました。
フェスやん、コントやん
「教えて能楽師」で伺った、本来の「能楽」はもっとリラックスして鑑賞するものだった、というお話は個人的にツボでした。かなり長時間にわたって演じられるものなので、観客は食べたり飲んだりしながら、演目の見どころがきたタイミングで舞台に注目するものだったそうで、(いくら何でもノリが違いますが)まるで音楽フェスみたいだと思いました。また、「初番目」と括られる演目の多くは神様が登場し、ワキ(役)が神様とはまだ知らずに「あなたは一体そこで何をしているのですか」と尋ねるところから始まるものが多い、と教えていただきました。まるで、お笑いトリオ「ロバート」のコントの導入パターンと一緒です。
体験が物を言う
「薪能」や「さらば青春の光」をきっかけに覗いた「能楽」の入口ですが、何となく押さえておきたいと思ってきた理由が、もう1つあります。せっかく日本人に生まれたので、「能楽」に限らず日本の伝統的なものについては、詳しくなくてもいいので、ちょっとは知っておきたい。今のところ、私は外国の方に日本の文化を紹介する機会はありません。けれども機会のある無しに関わらず、そういったものについて、たとえ「良いですよ!」という単純な感想であっても、体験のある方が実感がこもるというか、伝わり方が違うと信じているので、今後もちょこちょこと「やってみる」を実践していきたいと思います。
| 記事タイトル | 「能やな」「能なん?」「能やん!」 |
|---|---|
| 掲載日 | 2025年3月22日 |
| カテゴリー | ブログ |
| 表示数 | 333views |
