生成AIを指導する
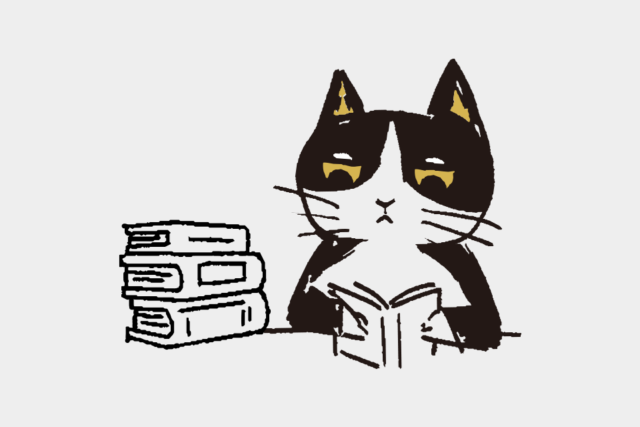
生成AIの問題点
生成AIは非常に便利ですが、使えば使うほど、いくつかの問題があることに気が付きます。そのひとつが「正確ではない情報を提供してくる」ことです。特に、大雑把なプロンプト(生成AIへの質問や指示)を与えた場合はその傾向が顕著です。これをうまくコントロールできるかどうかが「生成AIを有効に使えるかどうか」に直結しているように思います。
生成AIに嘘をつかせない
すでにいろいろなところで紹介されていますが、生成AIに正確ではない情報を提供させない、つまり嘘をついたり知ったかぶりをしたりさせない方法としては、以下のようなものがあります。ひとつは「具体的な質問にする」ことです。質問が曖昧な場合、いくつかの可能性を網羅するような曖昧で正確ではない回答が返ってくる場合があります。次に「出典を要求する」ことです。元になった情報を提供させるだけで、適当に組み上げた回答をすることが少なくなります。数ある手法の中で一番効果的なのは「わからない場合はわからないと答えさせる」ことかもしれません。生成AIは質問相手としてほぼ万能ですが、知らないことが無いわけではありません。「わからない」という回答を許容することで、知らないことを無理やり回答するのを防ぐことができます。他にも「考え方の手順を示させる」や「別の可能性も考えさせる」などの方法があります。
人に依頼するときと同じ
生成AIに嘘をつかせない方法をいくつか紹介しましたが、勘の良い方は「人に依頼したり指示したりするときと似ているな」と感じたのではないでしょうか。特に、上司と部下であったり、先生と生徒であったり、経験や知識に差がある関係性の場合、この依頼や指示の仕方が有効であることは想像できる方も多いのではないでしょうか。
生成AIは可能性に満ちた新人である
生成AIをよりよく使うには、生成AIが少し空気が読めなくて経験の浅い、そしてこちらの顔色を過剰に伺う新人だと思うと良いでしょう。ただ、その新人は非常に優秀で、誰よりも活躍する可能性が十分にあるのです。多くの科学者が予想するように、生成AIに指示を仰いで人間が仕事をするようになるのもそう遠くないのかもしれません。
| 記事タイトル | 生成AIを指導する |
|---|---|
| 掲載日 | 2025年9月13日 |
| カテゴリー | ブログ |
| 表示数 | 298views |
