日本語の具体と抽象
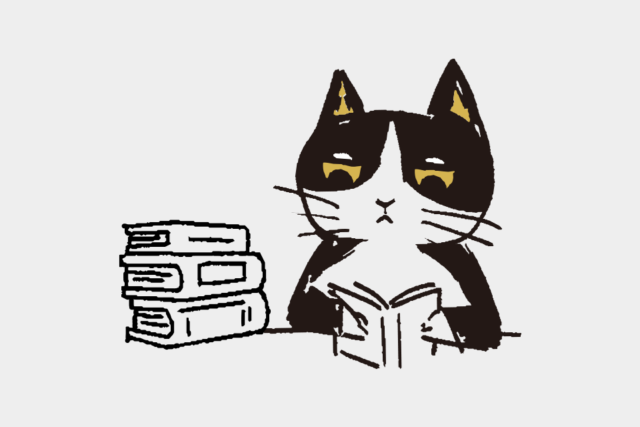
日本語の抽象度
日本語には、もともと日本で使われていた「和語(大和ことば)」と、海外から入ってきた「漢語(古く中国から来たもの)」や「カタカナ語」があります。「漢語」や「カタカナ語」は抽象度が高く、「和語」は抽象度が低いとされています。日本語に限らず、「抽象度」は高いと難しいような気がするし、低いと分かりやすく簡単な印象があります。
言葉をひらく
子どもや日本語の初学者(日本語以外を母語とする人)には、ふだん大人が普通に使っている言葉をひらく必要がしばしばあります。大人には少しも難しく感じない、例えば「決定」という言葉も、聞き慣れていない子どもや外国の人には「それ、なに?」となって当然です。そういう場合に「決定は、決定やろ」ではなく、何かを「決めること」と説明できることが大切ですし、多くのお父さんやお母さんたちは、ごく自然に日常的にそれをしていると思います。
具体化も楽じゃない
「決定」は漢語、「決めること」は和語なので、「言葉をひらく」とは抽象度の高いものを低くする(具体的に表す)ことと言えます。子どもや日本語初学者には「決めること」と説明するだけでは、まだ「?」の可能性もあり、そういう場合は何かを「決める」場面を具体的に示して理解を促したりします。一般的には(言葉以外でも)、物事を「抽象化する」ことは難しいとされていますが、言葉をひらく例を一つ取っても「具体化する」ことも、なかなか難しいものです。
抽象化はすごいけど
抽象化できることや、抽象的な概念を理解できることは確かに高度なことですが、そのために「できる」と評価もされやすいです。一方で、実は少しも簡単ではない「具体化ができる」人への評価は、あまり高くない印象があります。例えば、お母さんたちや、あらゆる状況において人を「ケアする」仕事をしている人などには、具体化の達人がたくさんいます。周囲はもちろん当事者自身も、もっとそのことを褒めちぎるべきです。
具体と抽象
以前「具体と抽象」をテーマにした講座をした際に、私の話の組み立てや伝え方が下手だったせいで、受講してくださった方に「それができたら何になるの?それが何の役に立つの?」というモヤモヤを抱かせてしまいました。「具体と抽象」が必要な場面は、あまりにも多岐に渡ります。今回取り上げた、日常的に「言葉をひらく」ことも、できること役に立つことのひとつです。
| 記事タイトル | 日本語の具体と抽象 |
|---|---|
| 掲載日 | 2025年9月20日 |
| カテゴリー | ブログ |
| 表示数 | 278views |
