乱数の誤謬
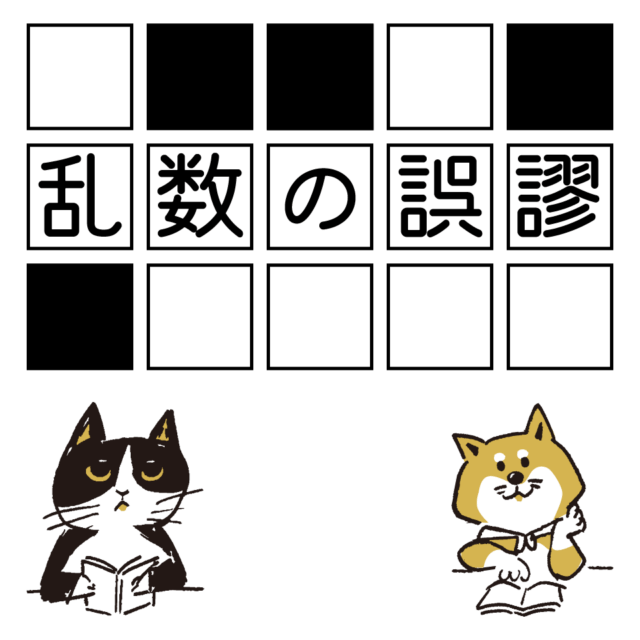
乱数の誤謬とは
「乱数の誤謬」とは、ランダムに発生するイベントにおいて、過去の結果が将来の結果に影響を与えると思い込む認知バイアス(思考の誤りや偏った傾向)のことです。「ギャンブラーの誤謬」とも呼ばれます。
乱数の誤謬の例
コインを投げ上げて「表」がでるか「裏」が出るかを予想するコイントスのゲームを例に考えます。前提として、表と裏が出る確率は全く同じ(50%)とします。このとき、9回投げた結果がすべて表だったとき、10回目に裏が出る確率が高くなりそう、と勘違いしてしまうのが「乱数の誤謬」です。それまでにどんな結果だったとしても、都度のコイントスで表が出る(あるいは裏が出る)確率は常に50%なのです。
クラスター錯覚と平均への回帰
乱数の誤謬を理解するには、「クラスター錯覚」と「平均への回帰」も知っておくと良いです。試行回数が少ない場合、ランダムなイベントであっても結果が偏り、クラスター(結果のまとまり)が形成されることがあります。これをみて、この仕組みが「ランダムではない」と思ってしまうのを「クラスター錯覚」と呼びます。また、試行回数が少ないほど偏った結果がでやすくなり、試行回数が多くなるほど結果のばらつきは小さくなります。これを「平均への回帰」と呼びます。
前述のコイントスでは、9回という少ない試行の中で「表」のクラスターが形成されたことについて、なにか特別なストーリーや確率の変化を見出したり、結果にばらつきがあることを過小評価したりした結果、乱数の誤謬が発生したと考えられます。
擬似乱数の採用
以上のことを踏まえて、商業用に乱数を用いる場合は工夫が必要です。たとえばスマホアプリなどで積極的に利用されている「ガチャ」のようなサービスでは、完全にランダムにしてしまうと通常の利用の範囲では「あたり」の発生確率に偏りが起こり、ユーザーの満足度が低くなることがあります。これを回避するために、擬似的な乱数を用いることがあります。例えば、箱の中に当選確率に基づく割合で「あたり」を入れておき、順番にくじを引いていく(くじは箱に戻さない)ようにすると、箱が空になるまでにはユーザーの希望する感覚に沿った確率で「あたり」を提供することができるようになります。
