住宅について考える
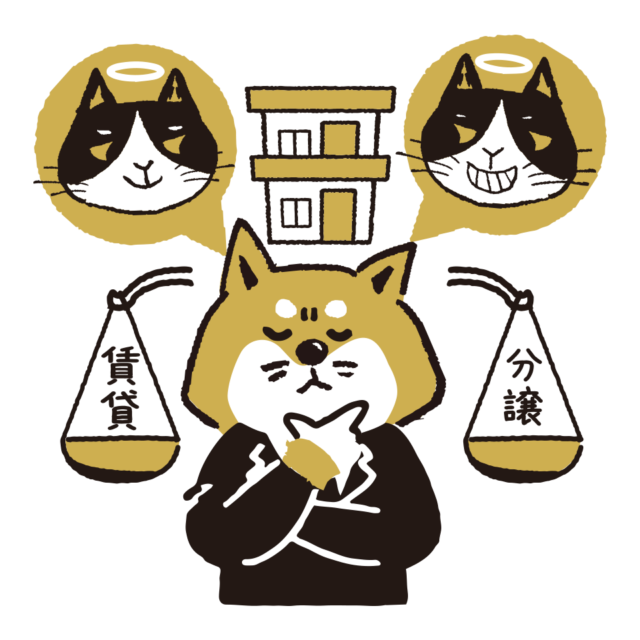
住宅は買う方が良い
人生100年時代の住処の確保
日本は、平均寿命が男女ともに80歳を超えています(参考01)。死ぬまで安心して暮らせる場所を確保することが、何より重要です(参考02)。退職する年齢は上昇傾向にありますが、それが70歳になったとしても、年金など退職後の収入に占める家賃の負担は小さくありません。2022年の総務省家計調査によると、持ち家の場合、住居にかかる費用(修繕維持費を含む)は月額14,000円程度でしたが、賃貸の場合は5万円を超え、公営住宅でさえ3万円以上の支出でした。また、他の支出項目を比較すると、持ち家の場合は住居に費用がかからない分、娯楽などにゆとりのある生活を送れていることが見てとれます(参考03)。
質とセキュリティの高さ
ローンを組んでマンションを購入した場合、月々の支払いが同等の分譲マンションと賃貸マンションとを比べると、分譲マンションの方がセキュリティや設備のクオリティが高い物件に住むことができます(参考04)。特に、防犯面や耐震性など「安全」に関わる部分は、単純には金額換算できない価値があると言えます。
住まいへのこだわりを実現
コロナ禍を機に「在宅ワーク」が一般的になり、自宅で過ごす時間が長くなったことで、住まいに対する関心も高まりました(参考05)(参考06)。より快適な居住空間を実現しようとしたとき、制約が多い賃貸では大規模なリフォームが許されることはほとんどありません。その点、購入した物件であれば自由にリフォームやリノベーションができます。また、新築のタイミングであれば、マンションであっても間取りから壁紙まで、細かく指定することが可能です(参考04)。さらに戸建ての注文住宅の場合は、サウナやシアタールームなど趣味の部屋を作ったり、DIYによって自らの手で時間をかけて理想を形にしたりできるのです。住まいへのこだわりが強ければ強いほど、購入以外の選択肢は考えられません。
資産形成は主目的ではない
近年の空き家率の上昇にともない、住宅を購入しても資産価値は乏しく売却も相続も難しいという考えが目立ってきました。しかし空き家率は地域差が大きく(参考07)、場所をきちんと選べば、住み続けた家屋に価値がなくなったとしても、土地の価値まで無くなることはありません。また、売却や相続を想定した資産形成としてではなく、住宅本来の「住むためのもの」という発想を持てば、購入して損をすることはありません。
参考資料
- 参考01「1 主な年齢の平均余命/令和4年簡易生命表の概況」厚生労働省
- 参考02「これからの高齢者は『2000万円では足りない』事態もあり得る/『老後資金2000万円問題』最新データで再計算してみた、あなたに必要な額は?」ダイヤモンド・オンライン/株式会社ダイヤモンド社
- 参考03「高齢者の持家世帯と借家世帯では生活費はどのくらい違うのか?/賃貸だと一生払い続けなければならない家賃、老後はどうする?」All About/株式会社オールアバウト
- 参考04「マンションは『購入vs賃貸』どちらが得?それぞれのメリット・デメリットを比較!」ブライトタウンブログ/遠州鉄道株式会社不動産事業部
- 参考05「コロナ禍でも好調、2020年度の家具・インテリア販売市場は過去最高更新へ―巣ごもり需要や在宅勤務拡大が追い風」PR TIMES/株式会社帝国データバンク
- 参考06「アフターコロナのライフスタイルを考える」ニッセイ基礎研究所/株式会社ニッセイ基礎研究所
- 参考07「都道府県別のその他空き家率/空き家政策の現状と課題及び検討の方向性」国土交通省住宅局
住宅は借りる方が良い
住居費を調整できる
賃貸の方が、世帯収入や家族構成に応じた物件への住み替えを容易に行えます。住居費は、収入に対して2〜3割程度の金額が理想とされていますが(参考01)、収入は自身の転職や世の中の景気など、さまざまな理由で増減します。また、人生という長いスパンにおいては家族の人数も変わるケースが多いことから、住み替えをスムーズに行える方が家計を調整しやすいのです。さらに賃貸であれば、固定資産税などの税金は不要な上、住宅の維持費や修繕費も、負担は少なくなります(参考02)。これは、修繕費などは物件の所有者に負担の義務があるためです。
転居しやすい
賃貸では、人生のターニングポイントでの転居が可能です。例えば、転勤や出産、子どもの独立、親の介護などに合わせて住み替えしやすいことは大きなメリットです。住宅を購入しても転居はできますが、まだ払い終えていないローンの処理や購入した物件の売却などを行うことは容易ではありません。また、あるアンケートでは約4人に1人が「近隣トラブルに遭ったことがある」と回答しています(参考03)。そのような回避困難なトラブルだけでなく、災害に見舞われて住宅が損壊した場合でも、賃貸であれば新天地を求めての転居を検討できます。
人生の充実
近年、ワークライフバランスへの意識が高まってきました。購入した家のために何時間もかけて通勤するよりも、職場に近い賃貸物件を見つけて、家族と過ごす時間や自分の時間を充実させたい人も増えています(参考04)。また少子化の影響で、子ども1人あたりにかけるコストが増えています(参考05)(参考06)。評判の良い学校に通いやすい場所へ家族ごと引っ越す、という選択も賃貸であればこそ実現しやすくなるのです。
「夢のマイホーム」は古い
かつては「結婚する」「子どもを儲ける」「マイホームを購入する」ことが、大人として「一人前」であり、理想像でもありました。しかし現在では「結婚をする」ことから当たり前ではなくなり(参考07)、生き方の選択肢が広がっています。もちろん、結婚して子どもを儲ける人生を歩んでいる人の方がまだ多数派ですが、マイホームの購入を検討する人は減ってきました(参考08)。その理由の多くは、少子化に加えて、共働きや転職が当たり前になったことなど、時代の変化によるものです。その上、かつては少なかったファミリータイプの賃貸物件が増えた昨今、いつかは不要になる子ども部屋を備えた広い住宅を購入して、その場所に縛られる理由はなくなったのです。
参考資料
- 参考01「家計で大きな割合をしめる住居費。平均家賃が高い・低い都道府県と節約ポイントを解説」ファイナンシャルフィールド/株式会社ブレイク・フィールド社
- 参考02「賃貸VS購入のメリットデメリットを比較。『住居費』はどっちが得?」SUUMO(スーモ)/株式会社リクルート
- 参考03「【近隣トラブルにあったことのある人の割合は?】男女500人アンケート調査」PR TIMES/株式会社帝国データバンク
- 参考04「Job総研による『2023年 ワークライフ実態調査』を実施 理想はプライベート重視7割 実際は仕事に偏りギャップ顕著」PR TIMES/株式会社帝国データバンク
- 参考05「子どもの減少と相反する一人あたり教育費の増加/経済のプリズムコラム No16」参議院
- 参考06「少子高齢化の時代、子ども一人あたりの教育費は増えた? 子育て世帯の気になる教育とお金の事情をデータで観察」データのじかん/ウイングアーク1st株式会社
- 参考07「図録▽未婚率の推移」社会実情データ図録
- 参考08「マイホームという虚像~これからの豊かさとは/経営コラム」株式会社日本総合研究所
